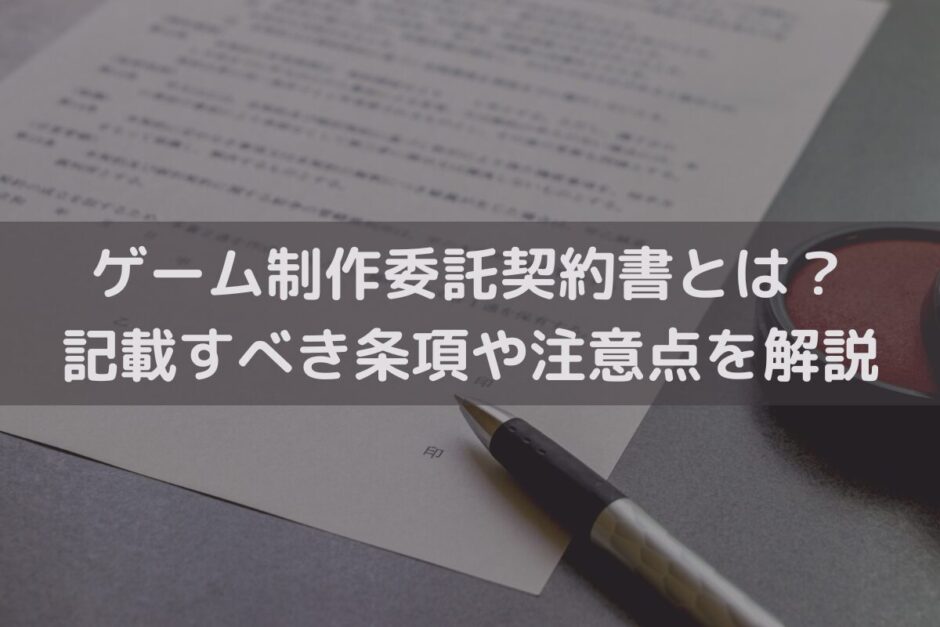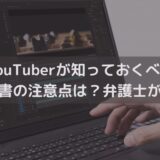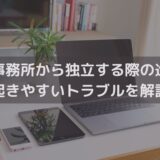ゲーム制作の委託・受託をする際は、契約書の締結が必須といえます。契約書を交わさなかったり不備があったりすれば、さまざまなトラブルの原因となりかねないためです。
では、ゲーム制作委託契約書に不備がある場合、どのようなトラブルが想定されるでしょうか?また、ゲーム制作委託契約書には、どのような条項を盛り込めば良いのでしょうか?今回は、ゲーム制作委託契約書の概要や不備がある場合に生じ得るトラブル、契約書に盛り込むべき条項などについてくわしく解説します。
なお、当サイト「エンタメ弁護士.com」はエンタメ法務に特化した専門家によるチームであり、ゲーム制作委託契約についても豊富な対応実績を有しています。ゲーム制作委託契約書の作成・レビューでお悩みの際は、エンタメ弁護士.comまでお気軽にご相談ください。
ゲーム制作委託契約書とは?
ゲーム制作委託契約書とは、ゲーム制作を社外の企業や個人に委託する場合に取り交わす契約書です。
完成品の納品を目的とする場合、ゲーム制作委託契約は民法上の請負契約にあたります。一方で、ゲーム制作業務への従事自体を求める場合(たとえば、プログラマーが自社に一定期間常駐し、自社従業員とともにゲームの開発作業に従事する場合など)には、準委任契約に該当する余地もあります。いずれに該当するのかによって適用される民法の規定が異なるため、契約の性質を事前に確認しておく必要があるでしょう。
なお、この記事ではゲームの制作を依頼する側を「委託者」、依頼される側を「受託者」と表記して解説を進めます。
ゲーム制作委託契約書に不備がある場合に想定されるリスク
ゲーム制作委託契約書に不備がある場合には、どのようなリスクが生じるのでしょうか?ここでは、主なリスクを4つ解説します。
- 修正対応の報酬について齟齬が生じる
- 著作権の帰属や二次利用についてトラブルとなる
- 相手方に問題がある際にスムーズに契約解除ができない
- 中途解約時の報酬請求でトラブルとなる
このようなリスクを避けるため、ゲーム制作委託契約書の作成は無理に自社だけで行うのではなく、エンタメ弁護士.comにご相談ください。
修正対応の報酬について齟齬が生じる
ゲーム制作委託契約書で業務範囲や仕様が明確になっていない場合、修正対応や追加対応分の報酬について齟齬が生じ、トラブルに発展する可能性があります。
基本的な考え方としては、ゲーム制作の受託者が契約した仕様に沿ったゲームを納品した場合、これにより報酬請求権が発生します。そのうえで、業務範囲外の追加対応や仕様外の修正を求めるのであれば、追加料金が必要です。
一方で、納品されたゲームが仕様に沿っていなかったり一部の業務が未了だったりするのであれば、当初契約書で取り決めた報酬の範囲内で(つまり、追加料金は発生せず)修正や追加対応を求められることとなります。
しかし、ゲーム制作委託契約書に不備があり、そもそもの業務範囲や仕様が明確になっていないのであれば、修正対応や追加対応が当初の契約の範囲内であるか否かの齟齬が生じ、トラブルに発展する可能性があるでしょう。
著作権の帰属や二次利用についてトラブルとなる
ゲーム制作委託契約書で著作権や二次利用についての定めがない場合、これに関してトラブルとなったり、委託者が想定した利用ができなくなったりする可能性があります。
著作権とは著作物を保護する権利であり、創作時点で自動的に発生するものです。著作権は原則として著作物を創作する者に帰属するのであり、創作にあたって費用を拠出した者に帰属するのではありません。つまり、「依頼して対価を支払っているのは委託者なのだから、著作権も当然に委託者に帰属するだろう」という理屈は通らないということです。
また、ゲームの製作委託では、「創作者(すなわち、著作者)とは誰なのか」も状況によって異なります。たとえば、委託者がざっくりと「こんな感じのゲーム」というアイディアを出してこれを受託者が具現化したのであれば、受託者が著作者となる可能性が高いでしょう。
一方で、委託者がゲームの細部までを決めて受託者は単にその指示どおりにプログラムを組んだだけであれば、委託者が著作者といえるかもしれません。また、双方が共同して創作したのであれば、両者がともに著作者となる共同著作となる余地もあります。
このように、著作権の帰属先は状況によって異なるため、双方が著作権を主張すればトラブルとなる可能性が高いでしょう。そこで、通常は契約書で著作権の帰属先を定め、このようなトラブルを抑止することとなります。著作権が委託者に帰属するとされる場合もあれば、著作権は受託者に残したまま、委託者に対して利用許諾をする場合もあります。
また、委託者として、そのゲームの二次利用を検討することがあります。たとえば、そのゲームの人気が出た際にアニメ化・映画化したり、グッズ販売をしたりするなどが挙げられます。しかし、受託者が著作権を有しており、当初の契約でこのような二次利用について定めていなかったのであれば、改めて許諾を得ようにも受託者から許諾が得られず、事実上二次利用が困難となるおそれもあるでしょう。
相手方に問題がある際にスムーズに契約解除ができない
契約の遂行に関して相手方に何らかの問題が生じた場合、契約を解除したいと考えることでしょう。たとえば、委託者が取り決めどおりに報酬を支払わない場合や、受託者に著作権侵害の問題が発覚した場合、受託者が制作中のゲームの内容を無断でSNSで公表した場合などです。
しかし、ゲーム制作委託契約書に解除に関する定めがなければ、スムーズな解除が困難となるおそれがあります。特に、SNSでの公表など民法などの規定だけでは明らかな債務不履行とまではいえない問題である場合、解除の可否について争いとなる可能性もあるでしょう。
契約書で禁止事項を明記したうえで、契約に違反した場合に契約解除できる旨を定めておくことで、問題発覚時の対応がスムーズとなります。
中途解約時の報酬請求でトラブルとなる
ゲーム制作が、何らかの理由で中途解除されることがあります。たとえば、委託者側の企業の方針転換などです。
そして、そのゲーム制作委託契約が請負契約である場合、受託者が既にした仕事の結果部分から発注者が利益を得られる場合、この部分を仕事の完成とみなして報酬請求ができるとされています(民法634条)。
しかし、実際には途中までの部分では「発注者が利益を得た」とまではいえない場合もあるほか、その部分に対応する報酬の算定が困難である場合も多いでしょう。報酬請求の可否や具体的な報酬額について齟齬が生じれば、トラブルに発展しかねません。
契約書で、中途解約時の報酬請求権やその場合の報酬の算定方法などを定めておくことで、このようなトラブルを回避できます。
ゲーム制作委託契約書に盛り込むべき主な条項
ゲームの制作委託契約書には、どのような条項を盛り込めば良いのでしょうか?ここでは、盛り込むべき主な条項とポイントを解説します。
- 業務範囲
- 納品・検収
- 契約不適合責任
- 報酬
- 著作権の帰属
- 表明保証
- 再委託
- 秘密保持
- 契約解除・損害賠償
業務範囲
契約書では、業務範囲を明確に定めます。ここでは、委託する業務内容を可能な限り特定し、別紙を添付するなどして可能な限り仕様も定めるべきでしょう。先ほど解説したように、この表記が曖昧であれば追加・修正対応にあたってトラブルとなりかねないためです。
納品・検収
契約書では、完成品の納品方法(DVDなどの媒体を納品するのか、所定のフォルダにアップロードするのかなど)を定めます。
併せて、検収についても定めておきましょう。検収は「納品後〇日以内に行い合否を通知する」旨を定めるとともに、連絡の煩雑さを避けるために「期間内に合否の通知がなければ合格とみなす」旨を定めることが一般的です。
なお、検収期間は1週間から2週間程度とすることが多いものの、ゲームの規模が大きく検収に相当期間を要することが想定される場合などには、1ヶ月程度など長めの期間とすることもあります。
契約不適合責任
契約不適合責任とは、納品した成果物が契約に適合していない場合に、受託者が問われる責任です。具体的には、補修や代金減額などの対応を求められることとなります。
民法の規定によれば、契約不適合責任を追及するには発注者がその不適合を知った時から1年以内に受託者に通知しなければなりません(民法637条)。とはいえ、この規定に従えばたとえば「納品から2年後に不適合が見つかったら、そこから1年以内に通知すれば契約不適合責任を追及できる」こととなり、受託者としては忘れた頃に補修を求められるリスクがあります。そこで、契約不適合責任の追及期間を「納品後〇ヶ月以内」とする定めを置くことなどが検討できます。
契約不適合責任については工夫し得るポイントが少なくないため、事前に弁護士へ相談したうえで条項を工夫すると良いでしょう。
報酬
契約書では、報酬について定めます。報酬は、誰が見ても「いつ、いくらの報酬を支払うのか」がわかるよう明確に記載しましょう。
ゲーム制作委託契約の報酬は納品時に一括で支払う場合もあれば、開発期間中、複数回に分けて支払う場合もあります。
著作権の帰属
先ほど解説したように、ゲーム制作委託契約書では著作権の帰属に関する規定が非常に重要です。
完成したゲームの著作権が委託者・受託者のいずれにあるのか、そして著作権が受託者に帰属する場合にはどの範囲で使用を許諾するのか、二次利用はできるのか、その場合のロイヤリティは制作委託報酬に含まれているのか別途であるのかなど、明確に定めましょう。
表明保証
表明保証とは、開発するゲームが他者の著作権や商標権などの知財を侵害していないことを、受託者が保証する条項です。委託者としては、すべての知財について表明保証を受けたいことでしょう。
一方で、商標権などとは異なり著作権は登録制度が採られておらず、この世に存在するすべての著作物を調べることは現実的ではありません。そのため、受託者としては「受託者の知り得る限り」侵害がないなど、保証範囲に一定の限定を加えるよう交渉すべきです。
再委託
ゲーム制作委託契約が請負契約に該当する場合、原則として、再委託は自由です。請負契約では「成果物の納品」こそが重要なのであり、その過程は重視されないためです。
とはいえ、ゲーム制作委託では「その人」や「その会社」に依頼したいのであり、無断で下請けに出されては困る場合もあるでしょう。その場合には、契約書に再委託を禁じる条項や、再委託に出す際は事前に委託者の書面での承諾を得るべき旨の条項などを入れることとなります。
秘密保持
ゲーム制作委託契約では、秘密保持条項を設けることが一般的です。これは、受託者側だけに義務を課すのではなく、双方がともに義務を負う形をとることが多いでしょう。業務遂行の過程で、受託者もノウハウなどを委託者側に開示する場合があるためです。
契約解除・損害賠償
契約違反や何らかの問題が生じた場合に備え、契約解除条項を設けます。ここでは、たとえば「違反を是正するよう催告し、催告から〇日以内に違反が是正されなければ契約を解除する」のように、解除へ向けた具体的なステップを記載すると良いでしょう。
併せて、相手方の債務不履行が原因で契約解除に至った場合、損害賠償請求が可能であることも明記します。契約内容などの状況によっては、賠償額の予定額を記載することもあります。
ゲーム制作委託契約書に関するよくある質問
続いて、ゲーム制作委託契約書に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
ゲーム制作委託契約書はひな型をそのまま使ってもよい?
ゲーム制作委託契約書の作成に、ひな型をそのまま使うことはおすすめできません。なぜなら、ひな型はあくまでもあるケースを想定した一例でしかなく、自社が締結しようとする契約実態に即しているとは限らないためです。契約実態に合わない内容の契約書を取り交わすことは、トラブルの原因となります。
そのため、ゲーム制作委託契約書はひな型をそのまま流用するのではなく、契約実態に合わせて作成すべきでしょう。ゲーム制作委託契約書の作成やレビューでお悩みの際は、エンタメ弁護士.comまでご相談ください。
ゲーム制作委託契約書に印紙は必要?
ゲーム制作委託契約書は印紙税法上の「請負に関する契約書」に該当することが多く、その場合には印紙の貼付が必要です。印紙税の額は契約書の記載の金額によって変動し、それぞれ次のとおりです。
| 契約書に記載の金額 | 貼付すべき印紙の額 |
|---|---|
| 金額の記載がないもの | 200円 |
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 400円 |
| 200万円超300万円以下 | 1,000円 |
| 300万円超500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超1千万円以下 | 1万円 |
| 1千万円超5千万円以下 | 2万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超10億円以下 | 20万円 |
| 10億円超50億円以下 | 40万円 |
| 50億円超 | 60万円 |
ただし、ゲーム制作委託契約書が「準委任契約」に該当する場合は、印紙税はかかりません。また、請負契約に該当する場合であっても、電子契約であれば印紙の貼付は不要です。ゲーム制作委託契約書に印紙が必要であるか否かは契約書の内容や締結方法によって異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
ゲーム制作委託契約書はエンタメ弁護士.comにお任せください
ゲーム制作委託契約書の作成やレビューは、エンタメ弁護士.comにお任せください。エンタメ弁護士.comはエンタメ業界に特化した専門家によるチームであり、弁護士・弁理士である伊藤海が発案しました。最後に、エンタメ弁護士.comの主な特長を3つ紹介します。
- エンタメ法務に特化している
- 専門家がチーム制で対応する
- 英文契約書にも対応している
エンタメ法務に特化している
エンタメ弁護士.comはメンバーの全員がエンタメ法務に特化しており、豊富なサポート実績を有しています。そのため、ゲームの開発委託契約に関しても、的確なサポートの提供が可能です。
専門家がチーム制で対応する
何らかの困りごとが生じても、どの専門家に相談すべきか迷うことも多いでしょう。専門家はそれぞれ保有資格によって対応できる分野が異なるほか、専門家によって得意とする分野も異なるためです。
エンタメ弁護士.comのチームには弁護士・弁理士のほか行政書士、社会保険労務士、司法書士、税理士・公認会計士が属しており、困りごとの内容に応じて最適な専門家が対応します。また、必要に応じて専門家がチーム制で対応するため、相談先に迷う必要はありません。
英文契約書にも対応している
ゲーム開発の委託や受託をする企業では、海外の企業や個人と取引する機会が生じることもあるでしょう。エンタメ弁護士.comは英文契約書にも対応しているため、海外との契約に関しても一貫したサポートが実現できます。
まとめ
ゲーム制作委託契約書について、概要や不備があった場合に生じ得るトラブル、契約書に盛り込むべき主な条項などを解説しました。
ゲーム制作の委託・受託をする際は、契約実態に即した契約書の締結が必須です。契約書に不備があれば、修正・追加対応の報酬について齟齬が生じたり著作権の帰属が曖昧となったりして、トラブルの原因となりかねません。契約書はひな型をそのまま流用するのではなく、弁護士へ相談したうえで、契約実態に合った内容で締結しましょう。
エンタメ弁護士.comはエンタメ法務に特化した専門家チームであり、ゲームの制作委託契約についても豊富なサポート実績を有しています。ゲーム制作委託契約書の作成やレビューでお困りの際は、エンタメ弁護士.comまでお気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。