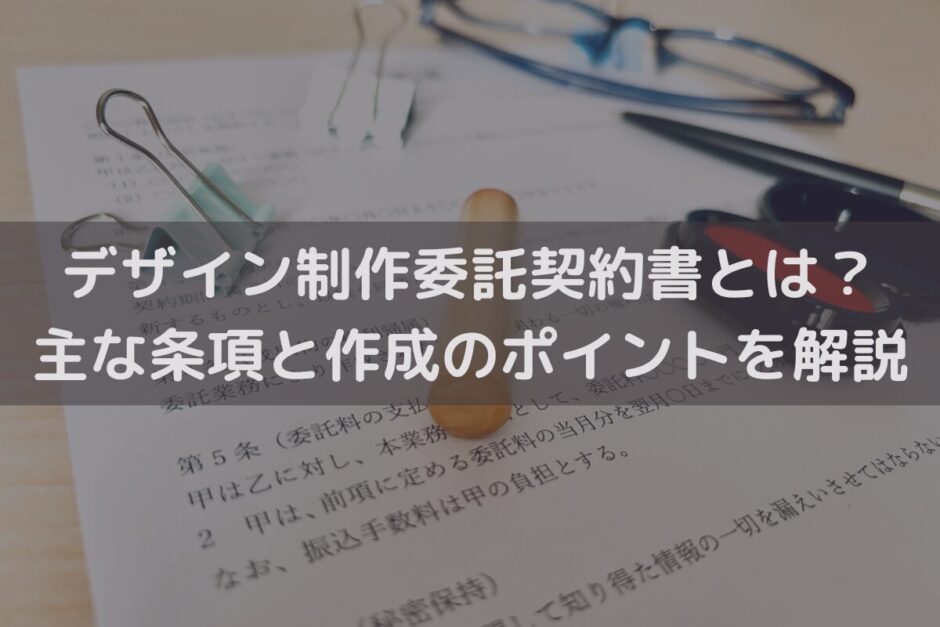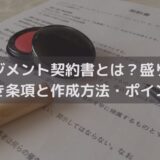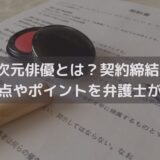デザイン制作は自社で行う場合もあれば、外部の企業やフリーランスなどに委託して行う場合もあるでしょう。外部の企業や個人にデザイン制作を委託する場合や、外部企業からデザイン制作を請け負う場合には、デザイン制作委託契約書の締結が必須であるといえます。
では、デザイン制作委託契約書は、法律上、どのような性質を有するのでしょうか?また、デザイン制作委託契約書にはどのような条項を記載すれば良いのでしょうか?今回は、デザイン制作委託契約書の概要やデザイン制作委託契約書に記載すべき条項、デザイン制作委託契約書の作成方法や印紙税などについて、弁護士がくわしく解説します。
なお、当サイト「エンタメ弁護士.com」は弁護士・弁理士である伊藤海がエンタメ法務に特化した専門家によるチームであり、デザイン制作委託契約書の作成サポートやレビューにも対応しています。デザイン制作委託契約書の締結でお困りの際は、エンタメ弁護士.comまでお気軽にご相談ください。
デザイン制作委託契約書とは
デザイン制作委託契約書とは、デザイン制作を委託する企業(以下、「発注者」といいます)と、デザイン制作を受託する企業やフリーランス(以下、「受託者」といいます)とが締結する契約です。
デザインの制作委託では、発注の対象が「物」ではありません。そのため、委託内容について齟齬が生じたり、デザイン制作の労力を理解しない発注者から気軽に「やり直し」を命じられたりするトラブルが生じる可能性があります。また、受託者が他者の知的財産権を侵害した成果物を納品した結果、発注者の信頼が低下するなどのトラブルも想定されます。
このようなトラブルを避けるため、そして万が一トラブルが発生した際にスムーズな解決をはかるため、デザイン制作委託契約書の締結は必須であるといえます。デザイン制作委託契約書の作成でお困りの際は、エンタメ弁護士.comまでご相談ください。
デザイン制作委託契約の種類
民法には、13種類の典型契約が定められています。たとえば「売買契約」に該当する場合、契約書に明記のない事項は民法上の「売買契約」に関する規定を適用して解決をはかることとなります。
しかし、「デザイン制作委託契約」は民法上の典型契約ではなく、その内容によって「請負契約」の側面が強い場合と「準委任契約」の側面が強い場合とに大別されます。また、両方の性質を併せ持つ場合も存在します。ここでは、請負契約と準委任契約について、それぞれ概要を解説します。
請負契約
請負契約とは、当事者の一方がある仕事の完成を約し、相手方が仕事の結果に対して報酬の支払いを約束することで成立する契約です(民法632条)。たとえば、注文住宅の建築委託が典型的な請負契約です。
請負契約では仕事の完成こそが契約の目的であり、受託者は仕事を完成させる義務を負います。仕事を完成させさえすればその過程は問われないため、原則として再委託も自由です。
準委任契約
準委任契約とは、当事者の一方が法律行為でない事務を相手方に委託し、相手方がこれを承諾することで成立する契約です(同656条、643条)。準委任契約の代表例としては、コンサルティング契約やシステム管理などが挙げられます。
準委任契約では仕事の完成は主目的ではなく、善管注意義務(善良な管理者の注意義務)をもって事務を遂行することが目的とされます。「その人(企業)」を信じて任せる契約であるとの前提があるため、発注者の許可を得た場合かやむを得ない事情がある場合を除き、原則として再委託はできません。
デザイン制作委託契約書に設けるべき主な条項とポイント
先ほど解説したように、デザイン制作委託契約書は民法上の典型契約ではありません。そのため、契約条項に規定がない事項について民法におけるどの条項を適用すべきかの判断が分かれ、トラブル解決が長期化するおそれもあるでしょう。
そのような事態を避けるため、デザイン制作委託契約書では民法を参照せずとも契約の内容が分かるよう、各条項を明確に定めておくことをおすすめします。ここでは、デザイン制作委託契約書に設けるべき主な条項とポイントを解説します。
- 契約の目的
- 納品と検収
- 対価
- 再委託の可否
- 知的財産権の帰属
- 非侵害保証
- 秘密保持
とはいえ、実際のデザイン制作委託契約書を的確に作成するのは、容易ではないでしょう。デザイン制作委託契約書の作成でお困りの際は、エンタメ弁護士.comまでご相談ください。
契約の目的
デザイン制作委託契約書では、契約の目的を定めます。
発注者としては、納品された成果物が契約内容に適合していない限り、あらかじめ取り決めた報酬の範囲内で受託者に対してやり直しなどを求めることが可能となります。これを、「契約不適合責任」といいます。契約の目的が曖昧であれば、契約不適合責任を追及しづらくなるでしょう。
また、契約の目的が曖昧であれば受託者としても「どこまでの業務が報酬に含まれるのか」が分からず、安心して仕事をすることができません。そのため、契約目的を明確に定めることは、発注者にとっても受託者にとってもメリットであるといえます。
なお、委託するデザインの内容によっては、契約書内に詳細な仕様までを明記するのが難しい場合もあるでしょう。その場合には別途仕様書を用意し、契約書には「別紙仕様書のとおりとする」などと定めることも可能です。
納品と検収
デザイン制作委託契約書には、納品方法と検収について定めます。
デザイン制作委託契約では成果物が物ではなく「データ」です。そのため、契約書では納品方法(「Eメールで送信する」、「所定の共有フォルダにアップロードする」など)と、成果物のファイル形式(「aiデータ」、「PDFデータ」など)を定めておく必要があるでしょう。
また、デザイン制作委託契約では、受託者がデザインを引き渡した時点で義務履行とするのではなく、その後発注者が検収をして、検収合格をもって義務履行とすることが一般的です。
とはいえ、発注者としても逐一検収合格の連絡をするのは手間でしょう。また、受託者としてはいつまでも検収合格の連絡がなければ、忘れた頃に修正依頼が入る可能性があり、不利益です。
そのため、「納品から〇日以内に検収の合否について連絡がない場合には、検収に合格したものとみなす」などの規定が多く用いられています。
対価
デザイン制作委託契約書には、対価の額または計算方法を定めます。デザイン制作委託契約の場合、対価は「請求書発行後〇日以内」などと定めることが一般的です。
ただし、そのデザインが今後継続的に直接の利益を生む可能性がある場合には、ロイヤリティを定めることもあります。ロイヤリティを発生させる場合には、ロイヤリティの計算方法についても明記しておきましょう。
再委託の可否
デザイン制作委託契約書では、再委託の可否について定めます。
先ほど解説したようにデザイン制作委託契約は請負契約に該当する場合と準委任契約に該当する場合とが存在し、いずれに該当するかによって再委託の考え方が異なります。そのため、無用なトラブルを避けるため、契約書には再委託の可否や再委託をする条件などを定めておくと良いでしょう。
やむを得ない場合を除いて再委託を禁止する場合もあれば、原則として禁止しつつ発注者から事前に許諾を得ることで再委託できるとする場合、再委託を自由とする場合などがあります。
知的財産権の帰属
デザイン制作委託契約書では、成果物の知的財産権の帰属について明記しましょう。
勘違いも少なくないものの、デザイン制作を外部に委託する場合は、そのデザインの著作権はデザイナーなどの受託者に帰属するのであり、対価を支払ったからといって自動的に発注者に帰属するのではありません。そのため、発注者に知的財産権を帰属させたいのであれば、その旨を契約書に明記する必要があります。
なお、デザインを発注者に知的財産権を帰属させるか否かは受託者にとって非常に重要なポイントであり、「著作権を譲渡するのであれば、別途相当の対価を受け取りたい」と考えるのが自然です。この条件を「後出し」をすれば契約が白紙となるおそれもあるため、知的財産権の帰属については契約の初期段階で交渉しておくべきでしょう。
非侵害保証
デザイン制作委託契約では、非侵害保証を定めます。非侵害保証とは、委託されたデザイン制作について、受託者が「他者の知的財産権を侵害していない」旨を保証する条項です。そのため、発注者としては「第三者の知的財産権を一切侵害していない」など、より広範囲での保証を求めたいことでしょう。
一方で、権利発生のために登録が必須となる商標権や意匠権などとは異なり、著作権を発生させるために登録は必要ありません。そのため、受託者がこの世にあるすべての著作権を調べきることは現実的ではなく、偶然一致したり偶然似通ったりすることは避けられないでしょう。
著作権侵害は「依拠性(つまり、元となる著作物の存在を知っていて模倣したこと)」がなければ成立しないとはいえ、第三者や発注者から侵害を疑われてトラブルとなる可能性は否定できません。そのため、受託者としては「受託者の知る範囲において第三者の知的財産権を一切侵害していない」など、一定の限度を設けたいと考えることが一般的です。
秘密保持
デザイン制作の委託にあたっては、業務上の秘密を開示すべき場合もあるでしょう。開示した秘密の漏洩を避けるため、契約の過程において知り得た情報を漏洩しない旨の条項を置くことが一般的です。
デザイン制作委託契約書の作成方法
デザイン制作委託契約書の作成には、テンプレートを活用して自社で作成する方法と、弁護士に依頼する方法があります。ここでは、それぞれの方法の概要を解説します。
- テンプレートを活用して自社で作成する
- 弁護士に依頼する
テンプレートを活用して自社で作成する
デザイン制作委託契約書のテンプレートは、インターネットを検索したり書籍を調べたりすれば比較的簡単に見つかるでしょう。
しかし、テンプレートはあくまでも「あるケースを想定した例」でしかないため、そのまま流用することは避けるべきです。内容を理解しないままにテンプレートを流用すれば、契約書の内容と当事者の認識との間に齟齬が生じてトラブルの原因となり得るためです。
そのため、テンプレートを活用するとしても、契約実態に合うように適宜条項を追加・削除したり変更したりしなければなりません。これには法令などによる専門知識が必要であり、自社だけで行うハードルは高いといえます。
弁護士に依頼する
デザイン制作委託契約書の作成は、弁護士に依頼して行うのがおすすめです。弁護士に作成を依頼することで、契約実態に即したデザイン制作委託契約書の作成が可能となるためです。
また、契約書の「正解」は1つではなく、どちらの側に立つのかによって望ましい条項は異なります。弁護士に依頼することで、自社にとって有利な内容で契約書を作成しやすくなるでしょう。
エンタメ弁護士.comは、デザイン制作委託契約書の作成支援について豊富な実績を有しています。的確なデザイン制作委託契約書の作成をご希望の際は、エンタメ弁護士.comまでご相談ください。
デザイン制作委託契約書の印紙税
一部の契約書には、「印紙」を貼付することで印紙税を納めなければなりません。印紙税とは、「印紙税法」に定めのある国税のことです。印紙税の課税対象であるにもかかわらず印紙が貼付されていなければ、税務調査で発覚した際に、本来納めるべき印紙税額に加え、その2倍の過怠税の対象となります。
では、デザイン制作委託契約書には印紙税が必要なのでしょうか?ここでは、デザイン制作委託契約書の印紙税について解説します。
準委任契約の場合
デザイン制作委託契約書が準委任契約に該当する場合、印紙は必要ありません。印紙税の課税対象である文書は列挙されており、準委任契約書は課税対象とされていないためです。
請負契約の場合
デザイン制作委託契約書が請負契約に該当する場合、請負金額に応じて次の印紙税の貼付が必要です。
| 契約書に記載の請負金額 | 貼付すべき印紙の額 |
|---|---|
| 金額の記載がない場合 | 200円 |
| 1万円未満 | 不要 |
| 1万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 400円 |
| 200万円超300万円以下 | 1,000円 |
| 300万円超500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超1千万円以下 | 1万円 |
| 1千万円超5千万円以下 | 2万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超10億円以下 | 20万円 |
| 10億円超50億円以下 | 40万円 |
| 50億円超 | 60万円 |
契約書に記載した請負金額が高いほど、納めるべき印紙税の額も高額となります。
(参考)電子契約の場合
昨今では電子契約も盛んとなっており、デザイン制作委託契約を電子で締結する場合もあるでしょう。デザイン制作委託契約を電子で締結する場合、印紙税はかかりません。印紙税の
課税対象は契約そのものではなく、「文書」であるためです。
デザイン制作委託契約書の作成はエンタメ弁護士.comへご相談ください
デザイン制作委託契約書の作成は、エンタメ弁護士.comにお任せください。最後に、エンタメ弁護士.comの概要と主な特長を紹介します。
エンタメ弁護士.comとは
エンタメ弁護士.comは、弁護士であり弁理士が発案した、エンタメ法務に特化した専門家によるチームです。いわゆる「士業」は資格者ごとに守備範囲が異なっており、「誰に相談すべきか」と迷うことも多いでしょう。また、相談する専門家を誤れば、たらい回しにされることもあるかと思います。
そこでエンタメ弁護士.comでは、弁護士・弁理士のほか、公認会計士・税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士がタッグを組みました。これにより、クライアント様の困りごとのスムーズな解決が可能となります。デザイン制作委託契約書について誰に相談すべきかお困りの際は、エンタメ弁護士.comまでお気軽にご相談ください。
エンタメ弁護士.comの特長
エンタメ弁護士.comの主な特長を3つ紹介します。
- 芸術・カルチャー・エンターテイメント法務に特化している
- 必要に応じて各専門家がチーム制で対応する
- 英文契約書にも対応可能である
芸術・カルチャー・エンターテイメント法務に特化している
エンタメ弁護士.comのメンバーは、全員が芸術・カルチャー・エンターテイメント法務に特化しています。
これらの業界はやや特殊ともいえ、業界実態にくわしい専門家は多くない印象です。エンタメ弁護士.comを構成する専門家は全員がこれらの分野に強みを有しているため、専門家を探す手間を大きく削減できます。
必要に応じて各専門家がチーム制で対応する
エンタメ弁護士.comでは、必要に応じて専門家がチーム制で対応します。
各資格者にはそれぞれ専門分野があるものの、複数の士業の領域にまたがる問題も少なくありません。エンタメ弁護士.comでは必要に応じて複数の専門家がチーム制で対応するため、総合的な視点で見た最良の解決策を講じやすくなります。
英文契約書にも対応可能である
エンタメ弁護士.comは、英文契約書にも対応しています。そのため、海外の企業や個人とデザイン制作委託契約書を締結すべき場面においても、一貫したサポートが可能です。
まとめ
デザイン制作委託契約書の概要やデザイン制作委託契約書に設けるべき主な条項、デザイン制作委託契約書の作成方法などを解説しました。
デザインの制作を外部に受発注する場合には、デザイン制作委託契約書の締結が必須です。的確な契約書を交わしておくことはトラブルの抑止力となるほか、トラブル発生時のスムーズかつ有利な解決にもつながります。
とはいえ、契約実態に合ったデザイン制作委託契約書を自社だけで作成するのは容易ではありません。無理に自社で作成した結果、必要な条項に漏れがあったり契約実態と異なる内容となっていたりすれば、無用なトラブルを生むおそれもあります。そのため、デザイン制作委託契約書の作成は、弁護士に依頼して行うことをおすすめします。
エンタメ弁護士.comはカルチャー・エンターテイメント法務に特化した専門家によるチームであり、デザイン制作委託契約書のレビューや作成にも対応しています。デザイン制作委託契約書の締結に関してお困りの際や、カルチャー・エンターテイメント法務について日ごろから相談できる専門家をお探しの際などには、エンタメ弁護士.comまでお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。